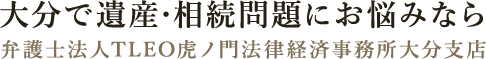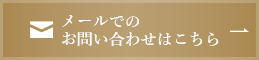遺言書・生前対策
このようなお悩みはありませんか?
- 遺言書の作成方法がわからず、どうすればよいか悩んでいる。
- 自分が書いた遺言書が法的に有効なものになっているか不安だ。
- 配偶者や子どもに確実に財産を引き継ぎたいが、方法がわからない。
- 相続で争いが起きないよう、遺言執行者を指定しておきたい。
- 遺言書が見つかったが、検認が必要だと聞いた。どのように対応すればよいか。
遺言書の作成

遺言書の作成方法には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を残す人)が全文を自筆で書き、日付と氏名を書いて押印して作成する遺言書です。費用をかけずに作成できる反面、法律で定められた形式を満たさないと無効になるリスクがあります。
一方で、公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書です。証人2名の立ち会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、形式不備による無効のリスクがありません。また、原本は公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もないでしょう。
当事務所では、依頼者のご事情や財産状況をしっかりとお伺いしたうえで、希望に沿った遺言書の作成をサポートいたします。
遺言の執行

遺言書に記載された内容を実現するためには、遺言書で遺言執行者を指定しておくことがおすすめです。遺言執行者は遺言者の最後の意思を実現するために、相続財産の調査・管理から、相続人への引き渡しまでを一貫して担当します。遺言執行者が指定されていると、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。
当事務所では、豊富な経験を持つ弁護士が遺言執行者として、遺言内容の実現をサポートいたします。相続税の専門家である税理士や、不動産登記の専門家である司法書士とも連携し、遺言執行に関するあらゆる手続きをワンストップで解決しますので、おまかせください。
遺言書の検認
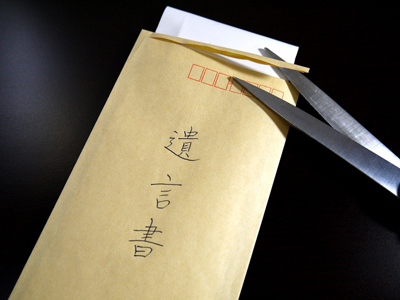
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の偽造を防ぐための重要な手続きです。具体的には、遺言書の原本を家庭裁判所に提出し、裁判所が相続人に遺言書を開示します。この手続きを経ないと、遺言書にもとづく相続登記などの手続きができません。
当事務所では、検認の申立てから相続人への連絡調整、裁判所での手続き完了まで、一貫してサポートいたします。必要に応じて他の相続人ともコミュニケーションを取りながら、スムーズな検認を目指します。
なお、2020年7月10日からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」を活用して、法務局で自筆証書遺言を保管している場合は、検認不要です。
当事務所の特徴

当事務所は1972年の設立以来、相続分野に力を入れてまいりました。家庭裁判所の所長を務めた弁護士をはじめ、豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。また、東京本店と緊密に連携することで、大分県においても質の高いサービスを実現しております。日本トップクラスの実績・ノウハウがございますので、安心しておまかせください。
相続問題は、法律だけではなく税務や登記など、さまざまな専門知識が必要です。そのため当事務所では税理士や司法書士との協力体制を整え、ワンストップでの解決をご提案しています。
初回相談は30分無料で承っており、料金体系も明確です。当日相談や夜間・土曜の対応も可能ですので、相続でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。